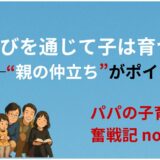《読み始める前に》
「なんで私がやらなきゃいけないの?」──顔全体で不満を訴える長女アキコ。
家族会議で決めた「お手伝いの習慣」ですが、すぐに軌道に乗ったわけではありません。
1年近くかけて育った“箸置き係”のエピソードです。
後段には、お手伝いをさせる価値や、始め方のヒントをまとめました。
パパの子育て奮戦記:第43号
長女アキコ(6歳)、次女クニコ(3歳)、ママ、パパ(私)、祖母(69歳)
嫌々の表情とナマケモノ
7月3日(日)、普段より遅めの朝食のことでした。
私はアキコに言いました。
「アキコ、箸置きお願いね」
これは昨年8月の家族会議で決めて以来、アキコの担当となったお手伝いです。
アキコは嫌そうな顔をして、まるで上野動物園のナマケモノのようにゆったりと動きます。
「なんで私がこんなことやらなきゃいけないの。やりたくねー。」と言いたげに、体全体で不満を表していました。
ママ:「そんなに嫌ならやらなくていいよ。見ている方が嫌になる。」
私:「どうせやるなら、気持ちよく、もう少しシャキッとしてやってくれないかな。」
アキコは黙ったまま動きません。(叱られて凍ってしまった?)
実母:「やりたくないなら(そんな場面を何度も目にしていた)、この仕事はクニコにやらせて、別の仕事をすればいいんじゃないかい。」
私:「だめだ。この仕事はアキコに決めたんだから。変えるのは仕事じゃなくて、アキコの心の方だ!」
そう言って一喝しました。普段はあまりないことですが、「シャキッとしてやりなさい。」と思わず声を強めました。
するとアキコは、上野動物園のナマケモノを止め、普通に手早く箸置きを並べました。
こうして朝食がようやく始まりました。
習慣として根づくまで
この日は庭のツゲの木を剪定するなど、外仕事も多い一日でした。
夕食時。再び「アキコ、箸置きお願いね」と言いました。
今度のアキコは、嫌々のそぶりも見せず、きちんと箸置きを並べました。
私もママも「ありがとう」と声をかけました。
箸置き係を始めてから、習慣になるまで、実に1年近くを要しました。
そこには、いくつもの揺れや葛藤がありました。
家族会議で決めた“役割”
もともと昨年8月の家族会議で「どんな子に育ってほしいか」を話し合い、
「めざす子ども──8<力を合わせる力>」が決まりました。
その具体的な方法として「お手伝いをさせる」ことになったのです。
話合いでは、
・家族の一員として自分がやれる貢献をする中で、社会性・協調性を育むことが大切だと意見が一致しました。
・小学校に入ればグループ活動や清掃など、協力できないと困ります。
(グループで学習するのに人任せで自分は何もしなかったり、みんなで清掃活動をしたりする際に自分ばかり何もしないで平気だったりするようでは困ると、正直思いました)
・毎日お手伝いを継続して取り組むことで、段取り力や自信も生まれると考えました。
・何よりも助け合い支え合うのが家族だという信念がありました。
それぞれが家族の一員としてできる貢献をすること、分かち合うこと。これができなければ家族ではないと思いました。『あなた作る人。私食べる人』ではいけないと思ったのです。食事を作れないなら、できる箸置きをすること。これは、能力の問題ではなくて、家族とは何かという信念・価値観の問題だと考えたのです。
そこで、毎日やれる仕事で、発達段階から言ってできそうな仕事は何かと考えた時、選ばれたのが「箸置き」でした。
食事のたびに必ずある作業であり、アキコ自身も「それでいい」というので、決まりました。
続ける中での葛藤
とはいえ、できたりできなかったりで、習慣にするのは簡単ではありませんでした。
-
箸置きがなくても食事はできる。
-
お腹が空いていて早く食べたい時には、箸置きをもどかしく思う。
-
アキコのゆったりペースにしびれを切らして、つい親が用意してしまうこともあった。
アキコが箸を置く・親がしてしまう・そもそも用意しないの間をずっと揺れていました。
箸置きの意味に気づく
6月、岡田多母さんの講演テープを聴きました。
「食事では箸を置いてよく噛むことが大事。そのために箸置きがある」と知りました。
箸置きは、単なる習慣ではなく“よく噛む”ことにつながる意味ある行為だと気づきました。
そこからは迷わず「必ず箸置きを置く」と決め、揺れることがなくなりました。
お手伝いは、子どもを成長させるという意図以外に、それ自体やる意味のあることでなければならないことを学びました。
1年かけて育った習慣
7月5日夕食。アキコはさらりと箸置きを用意しました。
この日は、誰からも注意されることなく自然に。
ここまで長くかかりましたが、ようやく習慣が根づいたことを実感しました。
「親の願いや信念がまず先にあり、そのうえで能力的にできて、かつ意味ある仕事を任せるなら、子どもは必ずお手伝いをきちんとやるようになる」
私はそう確信しました。
***********************
今、振り返ってみて
大学受験の高校時代でも、食器洗いを率先してやっていたアキコにも、お手伝いスタート時には、そんなこともあったなと、懐かしく思い出しました。
「あなた作る人、私食べる人」──そんな姿が家庭の当たり前になってはいけない、と強く思います。
原因として、まずお手伝いの価値をわかっていないことがあると思います。
拙著『うちの子、どうして言うこと聞かないの!と思ったら読む本』の中で「お手伝いの価値」を7つ挙げました。
価値1:思いやりのある子に育つ。
価値2:誇りを持ち、責任感と協調性のある子に育つ。
価値3:自立し、自信を持った子に育つ。
価値4:見通しを持って、物事をやり遂げられる子に育つ・・・以下、割愛
つまり、お手伝いをさせることは、教育的価値が高く、よいことづくめなのです。
では、どうすれば子どもが「自分からお手伝いする子」になるのでしょうか。
まず、お手伝いの意味や価値を親が自覚し、「お手伝いをさせる」と決意することが何よりも大切です。だからこそ、ここまでお手伝いの価値を長々と書いてきたのです。
そして、
▶️「子どもがまだ小さいから(←小さいうちからやらせたほうが身につきやすいです)」▶️「子どもにお手伝いをさせるよりも、親がしたほうが早いから(←確かにしばらくはそうでしょうが、いずれ元が取れます)」
▶️子どもにお手伝いをさせると、主婦としての仕事(立場)がなくなってしまうから(←子どもに手伝わせるのは、家事の一部に過ぎません)」
等々の言い訳を乗り越える必要があります。
そのうえで、先にあげた「炊事・洗濯・掃除」などの中から、本人ができることで、家族が助かること、しかも定期的にやる必要のあるお手伝いをやってもらうようにするとよいでしょう。最初にやらせるならば、配膳の準備や片付けなどがおすすめです。前掲書177p
むしろ子どもがまだ小さいうちにこそ、お手伝いをさせ始め、教え込んだ方がはるかにうまくいきます。子どもが小さいなりにできるお手伝い、例えば家族みんなの配膳、ーー箸を置くだけでもよいのですーー、片付けなどをさせるのです。
そこで、「家族だから助け合うんだよ」と言ってお手伝いをさせ、「ありがとう」と言って感謝の気持ちを伝えます。こうすることで、まず「家族は助け合うもの」と言う価値観(協調性のもとになります)と人の役に立つ喜びを教えるわけです。前掲書179p
このように書いていましたが、それは本稿で書いた「お手伝いをする子に育てる」がベースになっていました。
「子どもがまだ小さいから」「まだできないでしょう」などという理由でお手伝いをさせない親がいますが、中学生からでは完全に遅く、正直に言えば、小学校高学年からでも遅いでしょう。なぜなら、部活や塾通いなどで、お手伝いの時間がなかなか取れなくなるからです。それに、8歳を過ぎる頃から我が出てきて、簡単に親の言うことを聞かなくなってくるからです。
わが子に思いやりのある子に育ってもらいたかったら、助け合える協調性のある子に育ってもらいたかったら、自立し自信をもった子に育ってもらいたかったら、そして将来働ける子になってもらいたかったら(お手伝いは最も身近な職業教育の機会です)、お手伝いをさせましょう。
📝 自分に問いかけてみる時間
-
あなたの家庭では、「お手伝い=学びの場」と捉えていますか?
-
「まだ小さいから」「親がやった方が早い」──そんな理由で、子どもに体験の機会を奪っていませんか?
-
家族の一員として貢献できたと子どもが実感できる場を、つくれていますか?
📝 簡単なワーク
1今日から1つ、お手伝いを任せてみましょう。
👉 例:配膳、片付け、洗濯物をたたむ、玄関の靴を揃える。
能力的に無理がないか、本人がやりたいものか、家族が助かる意味のあるお手伝いかどうかを考えてお手伝いを選びましょう。
2その際は必ず「ありがとう」を伝えましょう。
👉 それは作業のご褒美ではなく、「あなたの存在が家族を助けている」という承認のメッセージになります。
***パパママとして成長したいあなたへ──フォローどうぞ***
「あったかい家族日記」は、長女アキコ(2025年8月現在27歳・既婚)と次女クニコ(23歳・公認会計士)の成長を、パパの視点で約20年間にわたり綴った実録子育てエッセイです。
*二人が幼児だった頃から大学入学、そして結婚前後までの家族の日々を記録し、累計アクセス数は400万を超えました。
*七田チャイルドアカデミー校長・七田眞氏にも「子育てに役立つブログ」として推薦された本連載は、So-netブログ閉鎖(2025年3月)を機に、「記録」と「今の視点」を重ね合わせて再編集した〈日々の記録に、“今”を添えた子育てエッセイ〉として、noteで再連載しています。
*この文章は、2005年7月5日にSo-netブログで公開された『お手伝いをする子に育てる』に、「今、振り返ってみて」を加筆した再構成エディションです。