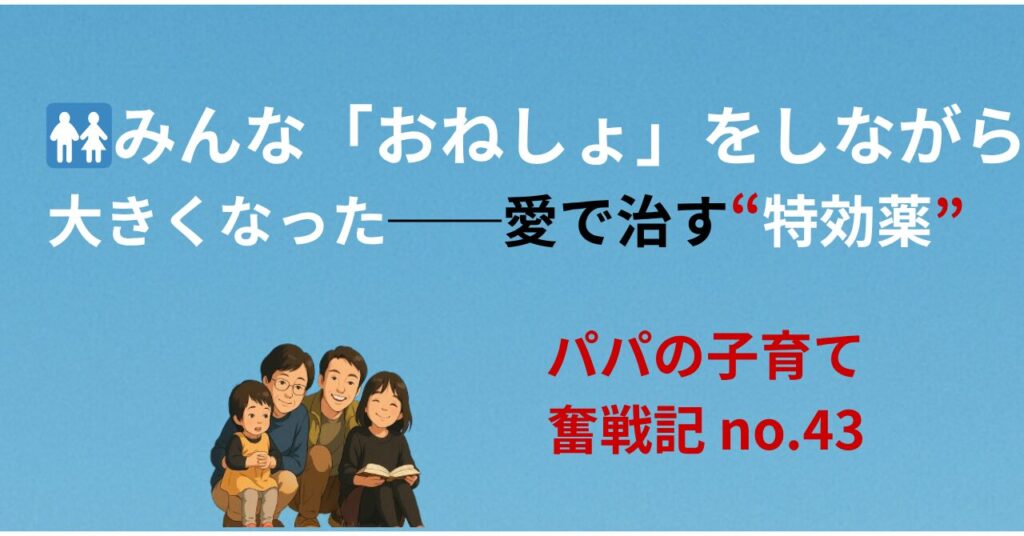🚻みんな「おねしょ」をしながら大きくなった──愛で治す“特効薬”
《読み始める前に》
おばあちゃんも、ママも、パパも。
みんな子どもの頃は「おねしょ」していました。
小学校高学年になっても、まだ時々「おねしょ」をする子もいます。
でも心配いりません。みんないつか、ちゃんと治ります。
後段は「おねしょ」に効く“愛の特効薬”も紹介します。
パパの子育て奮戦記:第53号
長女アキコ(6歳)、次女クニコ(3歳)、ママ、パパ(私)、祖母(69歳)
💤あーちゃんと寝る夜の出来事
7月16日(土)の夜。
アキコは「今日はあーちゃんと寝たい!」と強く希望し、一緒に寝ました。
翌朝、洗面所で、あーちゃんが何かを洗っているのを発見。
よく見ると──アキコのパンツ!
さては……?
🚪夢の中のトイレで…
あーちゃんが笑いながら言いました。
「やっぱり6時ごろ、トイレに行かせればよかったて。
ぐっすり寝てたから起こしたらかわいそうで……。
7時ごろブルブルって震えてたから、あの時が怪しかったね。」
パパ:
「きっと笑顔だったでしょう。夢の中でトイレの戸を開けて、
気持ちよさそうにオシッコしてたんだよ、きっと。」
ママ:
「私も経験ある。
夢の中でトイレに行ったら、戸が開いてて見られそうでできなかった。
そこでハッと目が覚めたの。」
あーちゃん:
「私は、トイレががけのような高いところにあって、怖くてできなかったね。」
パパ:
「二人とも、もらさなくてよかったというか、
(オシッコを気持ちよくできなかったので)悪かったというか……。」
「じゃあ、アキコは、ぼくに似たのかな。
ぼくは、夢の中で廊下を歩いてトイレの戸を開け、気持ちよくオシッコしたら……それは布団の中だった。あったかくて気持ちよかった(笑)」
家族全員:大笑い。
“おねしょ”が笑い話になる──そんな朝でした。
🍉おあずけになったスイカ
その日の夜。
大きなスイカをいただいたのですが、
「夜遅くに食べると、またおねしょするかもね」
ということで、今日はおあずけ。
パパ:
「うーん、食べたかったのに。早くから冷やしておいたのに……。」
でも、これを書いていてハッと気づきました。
明日から出勤。夜はダメなら、いったいいつ食べるんだ!?
よし、明日の朝、出勤前に
「スイカ、夜の早いうちに食べよう。昼間ぬけがけしないように!」
と釘を一本打っておかなきゃ。
(2005年7月18日)
**********************
今、振り返ってみて
小学校高学年でも5%ちょっといる
おねしょがなかなか治らず、心配しているパパママも多いでしょう。
実は、小学校6年生でもおねしょをする子が5%ちょっといます。
修学旅行の事前アンケートでは、
「夜、トイレに起こしてほしい」と書く保護者が毎年数人いました。
個別懇談とも合わせて、保護者がおねしょを心配する男児は、5%ちょっといました。
クラスで応援団長をするほど活発な子でも、そうしたケースがありました。
実は、私自身も、高学年になってもおねしょが治らず、母に心配を思い切りかけました。
私「6年生でも結構いますよ。いつの間にか治りますから心配いりません。 修学旅行では、確実に夜中に起こしてトイレに行かせますね。」
校長からは
「必ず起こして、絶対におねしょさせるなよ!」
と厳命されたものです。
要するに、小学校6年生になっても、5%ちょっとおねしょをする子はいるので特別ではないし、いずれ治るのです。
🧡おねしょの裏には“愛”がある
母は<お灸が効くと聞けばお灸>など、色々と試しましたが、結局効かず困っていました。
「今日はチベットだ!」(少しだけのおねしょ)
「今日はアフリカ大陸だ!」(たくさんのおねしょ)
と言いながら、お湯を布団にかけながらおねしょの後始末をしてくれた、母の姿を思い出します。
不思議と叱られた記憶はありません。
それより、お母さんには、「迷惑かけてごめんなさい。世話してくれてありがとう」という思いが残っています。
つまり、おねしょもまた、母からの愛情の記憶になるのです。
🌈愛をそそぐ“おねしょの特効薬”
寝る前にトイレに行くとか、寝る前にスイカなどの水分を取らないとか、そういったものではありません。
まさに、根本的に治療する特効薬です。
それは、本吉圓子さんの書いた『あふれるまで愛をそそぐ』という本の中で紹介している方法です。本吉さんは言います。
子どもにとっておしっこやうんちは、親を自分のほうに振り向かせる最高の手段なのです。
おねしょも、毎日何度もパンツを濡らすような頻尿も、やろうと思ってもできません。明日からやめようねと約束しても、止まりません。子どもの寂しい心、癒えない優しい子どもの心に、お母さんの愛がすーっと入ったとき、ピタリと止まります。
「不思議です」と皆さんがおっしゃいます。10歳の子どもでも13歳の子どもでも同じです。(157ページ)
つまり、「おねしょ」には、「お母さんの注目<愛>を得る」という肯定的な意図があって、お母さんの愛をそそぐことで、寂しい心、癒えない心が満たされた時、「おねしょ」がぴたりと止まるというのです。
おねしょをしたり、寝ぼけたりする子は、心が優しくて、感受性の豊かな子どもなのです。そういう子どもはつらいことがあっても、それを言うと、お母さんが悲しむことを知っていますので、何も言わないで、その辛さを自分1人で抱え込んでしまいます。それがおねしょや寝ぼけなどになって出てくるのです。
ですから、おねしょや寝ぼけなどを叱るのは全く見当違いのことです。それよりもおねしょをする子どもの心の辛さ、わだかまりを理解し、それを取り除いて、心に安らぎを与えてあげること—それがおねしょを直す最善の方法なのです。(148ページ)
本当に、愛をそそぐだけで、おねしょは治るのでしょうか?
論より証拠、本の中にいくつも実証例が載っていました。
1つだけ紹介します。
抱っこは大切?もう4歳になったのに?まさかとは思ったのですが、その言葉にすがる気持ちで、その日家に帰ってからは、とにかく抱っこしました。
不思議なことにその日おねしょはなし。そして、意味不明だった娘のおしっこ行為はピタリとなくなりました。今、思い出しても、これには主人も私もびっくりでした。
思い返してみれば、下の子が生まれてから弟中心の生活になってしまい、娘が「ママ抱っこして」と言ってきても、「ちょっと待ってね」とか「あとでね」という言葉が多かったかも。娘はとても我慢していたんだなぁと反省しました。
今、娘は小学1年生になりました。いまだに、時々「抱っこして」といいます。もう1年生なのにと思ってしまうのですが、そんな時は先生の話を思い出し、できるだけ抱っこするように心がけています。(153ページ)
この場合、愛をそそぐ手段が「抱っこ」なわけです。
この本に載っている他の事例も読むと、朝のグズグズが治ったり、噛みつきまでよくなっています。ママが愛をそそぐことで、こんなにも多くのことが好転するのかと驚かされます。
まさに、愛をそそぐことは、最高の特効薬なのです。
📝 自分に問いかけてみる時間
おねしょ、朝のグズグズ、噛みつき…子どもの問題行動は、満たされない心、ビタミン愛の不足からきているかもしれません。
10歳の長女が帰宅するなり、ママに「ねえ、ぎゅーして!」とリクエストしていたシーンを思い出します。その後、ぎゅーされて元気になった長女は、「ママがいると安心する」と言っていました。園や学校は、それなりにストレスのあるところです。家庭で子どもたちは、元気チャージすることで、明日の学校生活への英気を養っているのです。
1. 家庭が「元気チャージできる場」になっていますか?
2. 下の子ばかりでなく、上の子の心もちゃんと満たしていますか?
「ぎゅーして」「一緒に遊んで」という子どもの欲求をスルーしていませんか?
📝 簡単なワーク
🌼 ステップ1: 抱っこしたり、「大好きよ」と声をかけたりしてみましょう。
学校や園の出来事を、関心をもって聞いてあげるだけでもOK。
🌿 ステップ2: 年上の子にこそ、特別な時間を。
一緒にお菓子を作る、散歩に行く、10分の読書タイム──
“心の抱っこ”を意識してみてください。
💡愛をそそぐことは、最高の特効薬です。
***パパママとして成長したいあなたへ──フォローどうぞ***
「あったかい家族日記」は、長女アキコ(2025年8月現在27歳・既婚)と次女クニコ(23歳・公認会計士)の成長を、パパの視点で約20年間にわたり綴った実録子育てエッセイです。
*二人が幼児だった頃から大学入学、そして結婚前後までの家族の日々を記録し、累計アクセス数は400万を超えました。
*七田チャイルドアカデミー校長・七田眞氏にも「子育てに役立つブログ」として推薦された本連載は、So-netブログ閉鎖(2025年3月)を機に、「記録」と「今の視点」を重ね合わせて再編集した〈日々の記録に、“今”を添えた子育てエッセイ〉として、noteで再連載しています。
*この文章は、2005年7月18日にSo-netブログで公開された『オシッコをもらさない工夫。その裏には……』に、「今、振り返ってみて」を加筆した再構成エディションです。