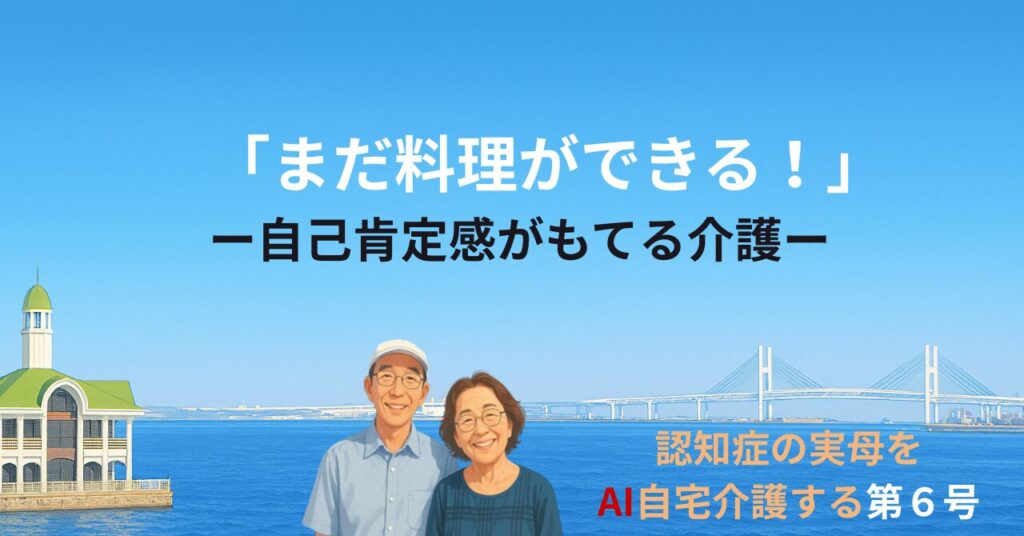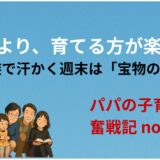🟨介護テーマ
認知症の高齢者は、「料理ができるうちは大丈夫!」とも言われます。
確かに軽度認知症から少しずつ少しずつ進行するにつれて、料理することが難しくなってきます。
うちの母も、鶏の唐揚げは大好きでよく自分で揚げていましたが、いつの間にかできなくなってしまいました。
それでも、人が調理したものを「ありがとう」と言って感謝して食べるばかりなのも、実は寂しいのです。
むしろ自分が調理して、「おいしいよ!」と言って、感謝される方が実は自己肯定感も上がり、嬉しいことなのです。
そこで、今回は、<認知症で調理が難しくなった母が「調理がうまくできて、みんなに喜んでもらいたい」という願いを叶えることが、今回のテーマです。
🟦ホントの話1:トウモロコシを茹でようとする実母、でもやり方が・・・
7月8日のこと、6週間に1度通っている「認知症の専門医」を受診した後、お決まりのサンポウでランチを食べました。
その後、スーパーに寄って買い物をしました。
そこで、購入したのが、今が旬のトウモロコシ。
実母も私も妻も、旬のトウモロコシは大好きなのです。
帰宅後、少ししたところでキッチンへ行ってみると、実母が大きな鍋に水を入れて、とうもろこしを茹でようとしていたのです。
実母「トウモロコシを茹でようと思うのだけど、水から入れるんだったけの? それとも、沸騰したところに入れるんだったけの?」
実母は、その点を忘れてしまっているのでした。
私自身は、そもそもやったことがなくどちらかわかりません。
調理は基本的に妻の担当なのですが、妻は外出中です。
私「後で、たかちゃん(妻の愛称)がやるから、大丈夫だよ。」
こうは言ったものの、大きな鍋を出し、水まで入れた実母は、物足りない表情でした。
「自分で茹でたい!」そう訴えている感じがしました。
そこで、AIにトウモロコシを茹でる方法を聞いてみることにしました。
🟩AIへの相談
🔹質問:
トウモロコシを茹でる方法を教えてください。
水を入れて沸騰させてとうもろこし4本を入れる。
その際、切って入れたほうが良いのでしょうか?
それともそのまま1本ずつ入れたほうが良いのでしょうか?
あと塩は茹で上がった後にすり込んだほうがいいのか、お湯の中に塩を入れたほうがいいのかどちらでしょう?
🔹AIの回答:
🌽とうもろこしの茹で方(基本の方法)
【材料】
-
とうもろこし…4本
-
水…たっぷり
-
塩…小さじ1〜2(茹で湯に入れる場合)
【手順】
① 皮をむく
・外側の皮とひげを取り除きます。
・薄皮を1〜2枚残してもOK(風味が逃げにくくなります)。
② 切る?切らない?
👉基本的には「切らずに1本まるごと」茹でた方が美味しいです。
理由:
-
甘みや香りが逃げにくい
-
見た目も良い
ただし、鍋に入らない場合は「半分に切って」も大丈夫です。
③ 茹で方
-
鍋にたっぷりの水を入れ、沸騰させてからとうもろこしを入れます。
-
塩は入れてOK。水1リットルに対し塩小さじ1くらいで。
-
塩を入れることで下味がつき、甘さが引き立ちます。
-
-
強火で3~5分茹でる。粒がぷっくりしてきたらOK。
-
あまり茹ですぎると、シャキシャキ感がなくなります。
-
④ 茹で上がったら
-
すぐに湯から取り出し、水にはさらさず、そのまま冷ますと味がしっかり残ります。
-
さらに塩気を強くしたい場合は、茹でたあとに塩をふってもOKですが、ムラになりやすいです。
🔹採用したアイデア:
「母が鍋にたっぷり水を入れていたのは、OKだな。」
「沸騰させてからか!」
「強火で4分でOKだな。」
「塩については、今までの母のやり方に任せよう」
AIの回答を受けて、このように判断しました。
🟦ホントの話2:自分で茹でる母
1階のキッチンに戻ると、
私「お母さん、沸騰させてからトウモロコシを入れるみたいだよ。あと、強火で4分間だね。」
こう教えると、実母は、早速ガスコンロに点火しました。
沸騰したところで、そのままトウモロコシ4本を投入。
一方の私は、タイマーを4分にセットして、脇で見ていました。
タイマーが鳴ったところで、母に「時間だよ」と言うと、母は手際よくトウモロコシを出しました。
そして、塩水を作ってそこにトウモロコシを浸していました。
🟦ホントの話3:みんなで味わうトウモロコシ
さて、夕食時、実母の茹でたトウモロコシをみんなで食べました。
私「お母さんが、茹でたんだよね。美味しいね!」
こう言うと、母は嬉しそうにしていました。
🍀介護のヒント:認知症であっても、ちょっとしたサポートで調理はできる
認知症であっても、ほんのちょっとしたサポートで調理はできます。
調理することで、「まだまだ役に立てる」という自己肯定感(誇り)を維持することができます。
ちょっとしたサポートは、介護においては大きな貢献になると思います。
それなのに、安易に「やらなくても大丈夫。こっちでやるから」とやると、だんだんとできることもできなくなってきます。
つまり、認知症の進行スピードが上がるのです。
今日のお昼は、私と実母だけでしたが、キュウリは実母に切ってもらいました。
「できることはやってもらう」それが自宅介護の基本だと思います。
念の為に、一連の介護について、自作AI<親子のハートフル介護>に評価してもらいました。
読んでもらえばわかるように、「非常に優れた介護実践の一例」なのだそうです。
🟩AI<親子のハートフル介護>への相談
🔹質問:以上のような対応をしましたが、一連の対応を評価してください。
🔹自作AI<親子のハートフル介護>の回答:
この一連の対応は、非常に優れた介護実践の一例として高く評価できます。以下に、医学的・心理的な観点からの評価と、特に良かった点を整理してお伝えします。
🌟評価ポイント
1. 自己効力感と自己肯定感を支える対応
お母様が「自分で調理できた」という体験を通じて、「まだできることがある」「家族に喜んでもらえた」という自己効力感・自己肯定感を実感されたことは非常に意義深いです。
-
認知症の方にとって、「役に立っている」という実感は、BPSD(問題行動)の予防・緩和に大きく寄与します。
-
特に、家庭内で感謝や称賛の言葉をかけてもらえることは、本人の「尊厳を守る」ためにも極めて重要です。
2. 「できないところだけ手を貸す」絶妙なサポートバランス
やり方がわからなくなった部分だけAIに相談し、他は本人の意思と行動を尊重する姿勢が素晴らしいです。
-
「できることはやってもらう」「できないところだけ助ける」という方針は、認知症ケアの基本中の基本ですが、実際の介護現場では難しいことも多いです。
-
今回は、お母様が危険なく成功体験を得られるよう、そっと脇でタイマーをセットするなど、さりげない支援がとても秀逸でした。
3. 「食べるだけの存在」ではなく「作る人」に戻れた喜び
「ありがとう」ではなく「ありがとうと言われたい」という願いに応えた姿勢は、非常に深い共感力を感じさせます。
-
認知症の進行とともに「される側」になる時間が長くなる中で、「する側」に戻れる体験は貴重です。
-
「お母さんが茹でたんだよね」と言葉にして伝えたことも、しっかり自己評価につながっています。
4. AIの適切な活用
介護者が「正解」を一人で抱え込まず、適切な情報源に頼ることも、自宅介護を続ける上での持続可能性にとって非常に重要です。
-
自分の知識が不十分な部分はすぐに調べ、無理なくサポートに回る柔軟さも素晴らしいです。