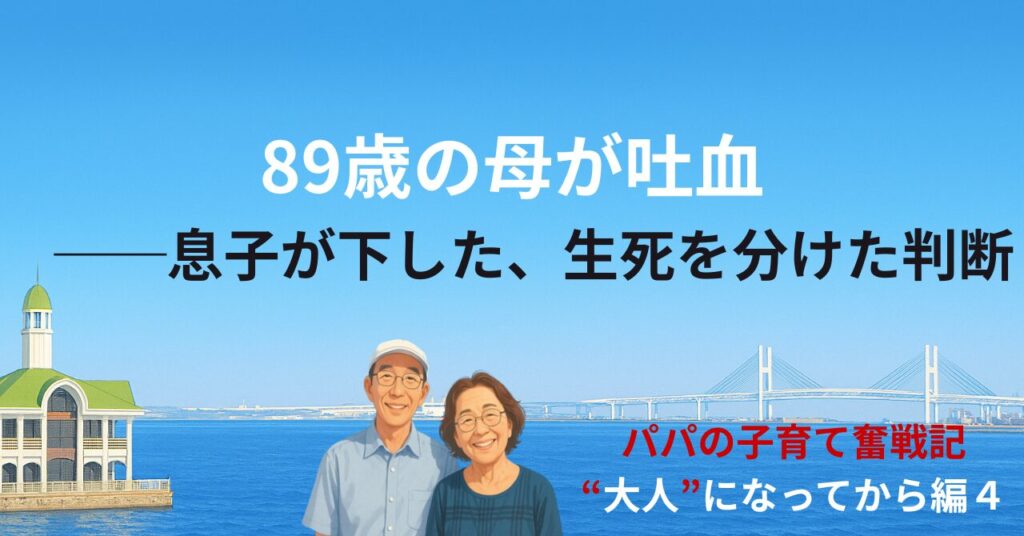《読み始める前に》
子どもが就職(今年4月次女、長女は4年前就職)、結婚(長女は一昨年)して子育て完了と前後して、親の介護が始まります。
89歳の実母にしても、8年前から認知症の専門医のところに通院していますが、月に1回、私が車に乗せて連れて行きます。
今回は、通院の帰り道、母が突然吐血した経験をもとに、生死・明暗を分けた行動についてお話しします。
パパの子育て奮戦記:大人になってから編 第4号
長女アキコ(27歳)、次女クニコ(23歳)、ママ、パパ(私)、祖母(89歳)
通院の帰り道、突然吐血
10月2日木曜日、月に1度の通院に連れて行きました。
診察後の帰り道、大好きな「五目うま煮そば」を食べることと、その後の買い物が通院の楽しみになっています。
母は、いつものラーメン屋に寄って、「五目うま煮そば」を食べていました。ところが、母は、6割ほどしか食べず、帰りにスーパーでの買い物を勧めても、寄らずにすぐに帰りたいと言いました。
約1時間の帰り道のちょうど半分を過ぎたところで、助手席に座っている母を見ると、なぜか額に汗がにじんでいました。「もう暑くないのにな」と不思議に思って見ていると、突然食べたラーメンを吐きました。
すぐの車を止めたのですが、ラメーンばかりでなく、吐血していました。それもはっきりとした血を。
ここで判断を誤ると、命が危ない!
そう直感しました。
かかりつけ医か地元の病院か
幸いなことに、ラーメンを誤飲することなく、意識ははっきりとしていて、話したり、助手席から出て立つこともできていました。
母「自宅に戻っておくれ。」
私「ダメだよ。血を吐いてる。医者に行かなきゃ。」
母は、吐いたらスッキリとしたのか、自宅か地元の病院に連れて行けと言います。
私は、8年間通っていて、事実上のかかりつけ医S医師のところに戻って診察してもらうのがベストだと判断しました。これまでの母の治療データがあるからです。午前中も脳内の撮影をしたばかりでした。7月の血液検査のデータもあるはずです。
とりあえず電話するも、ちょうど1時半でお昼休み。「〜午後の診察は2時半から〜」という留守電でつながりません。
母は、自宅か地元の病院に連れて行けというのですが、すぐにS医師の元に向かいました。
救急判断とS医師の的確な行動
30分後、S医師のところに着きました。まだ、昼休み中で閉まっていましたが、インターホンを押して開けてもらい、吐血したこと、事実上のかかりつけ医であることを話し、診察してもらいました。
結果は、<胃の中での出血ということで、大きな病院で診てもらった方が良い>という判断で、すぐに県央基幹病院に電話をしてくれて、紹介状も書き、救急車を呼んでくれました。
おそらくこの間、20分ぐらいです。
程なく救急車が到着しました。
私は一旦は一緒に救急車に乗ったのですが、本人の意識ははっきりとしているし、血圧等も正常だということで、同乗せずに自分の車で後を追うことになりました。
病院到着──次々と迫られる判断
赤信号でもかまわず進める救急車と違い、私は随分と遅れて病院に到着しました。母はすでにベットに寝かされていました。
しばらくすると担当医から、
①輸血することになった場合の輸血の許可
②胃カメラを使うことの許可
③胃の出血を止めるために、今飲んでいる血液をサラサラにする薬を止めることの許可(治療方針)
について、それぞれのリスクの説明のを聞いた上で、承認したという書類にサインを求められました。
この段階で、午後3時半、吐血から2時間後のことです。
母は、<帰宅か地元の医者に連れて行ってほしい>と私に話したのに、S医師のところに戻る判断をした私を怒っていました。
もし母の判断通りに行動していたら、こんなにスムーズにしかも早く医療判断はできなかったと思います。
そもそも救急車をすぐには呼べなかったと思いますし、かかりつけ医の判断とこれまでのデータが紹介状という形で基幹病院の担当医に渡っていたことが大きいと思います。
つまり、認知症で高齢者の母の判断に沿うのではなくて、たとえ怒られても、息子の私が判断するのが正しいということです。
的確な判断の下に、早めに的確な治療を受けた方が、母も良いわけですから。
胃潰瘍と判明、入院へ
胃カメラによる検査の結果、少なくとも1か所から血が出ていることが判明しました。胃潰瘍による出血だったのです。
担当医によれば、入院治療が必要で、順調なら1週間ほどで退院できるとのことでした。
「個室」を選ぶという決断
もう一つの判断が、「個室」という選択でした。お見舞いができるのは、個室だけというお話だったので、1日7,700円かかるとのことでしたが、迷わず個室を選択しました。
会話しないと、本人が寂しがるし、認知症を悪化させないためにも不可欠だと判断しました。
あと、約5年前の緊急入院では、どうして病院にいるのかが分からず、パニック気味になっていましたから。
今回の入院でも、やはり落ち着かず、救急車で病院に運ばれたのに、ここが介護施設のように勘違いしたり、点滴をしているのに病院であることがなかなか納得できず、落ち着かない状態でした。看護師さんに、私が一緒にいてほしいと言われてほどです。
ですから、私がお見舞いすることで、状況を説明したり、話し相手になったりすることが不可欠なので、「個室」を選択しました。
個室で見れるTVも契約しました。
あとは入院にあたっての説明を受け、入院時必要なもの、面会時間が午後2時から午後5時の間ということを確認して、入院関連の書類にサインしました。
病院を後にしたのは18:45、帰宅は19:20でした。
1週間ほどで退院
翌日の午前、胃が空っぽになった状態で、もう一度胃カメラによる検査をした結果、出血は3か所で出血を止める治療が始まるとのことでした。
詳しい担当医の説明は省きますが、治療がうまくいけば、1週間ほどで退院ということでした。
最初の2日間は、ご飯は一切なしだったものの、それがお粥になり、普通のご飯になりで、本人も翌日には自分でトイレに行きました。
入院したのが10月2日(木)で退院したのが10月10日(金)で、ほぼ予想通りの退院でした。
入院中のお見舞い──毎日の1時間が支えになる
午後2時から5時までの面会時間でしたが、結果として1日もかかさずに面会しました。平均1時間15分ほど(最小で45分、最大で2時間余り)
普通のおしゃべり以外に
・ここが県央基幹病院で、そこに入院していること
・吐血して救急車で運ばれたこと
・うまく治療が進めば、1週間で退院できること
は、毎日話すことになりました。
持って行って退屈しのぎになったもの・母に好評だったものは
・家族アルバム4冊(TOLOT製)
・私が過去に作ってあげた「母の伝記」
・母のお気に入りの本
・新聞
・保湿クリーム(塗ってあげることで、スキンシップにもなりました)
・タオルケット
でした。

母にとって、病室に置いていて一番良かったのは、携帯電話かもしれません。母は、毎晩電話をかけてきました。午前中も。
「寂しい」「退屈」というのはそうだと思うのですが、
「地獄だ」「死にたい!」というのには、少々まいりました。
***********************
今、振り返ってみて
「認知症の母が突然の吐血。正しかったのは“怒られる覚悟”で下した判断でした。」
89歳の母が突然吐血。
「すぐに自宅に戻りたい」という母の願いを振り切って、私はかかりつけ医のもとへと車を走らせました。
その後、救急搬送、入院、そして個室での療養。
入院生活の中で私が実感したのは、お見舞いは単なる付き添いではなく、“認知症の命綱”になるということでした。
食べたばかりのラーメンといっしょに吐血した瞬間の母の辛い表情。
そして、母の意思に反してS医師のもとに引き返した判断は、やはり的確だったと思います。
「個室」選択と、毎日のお見舞い
もうひとつ、あのとき「個室」を選んだことも、正解でした。
(母は「お金がかかるから個室はいらない」と言っていました)
迅速な診察と適切な医療を受けられただけでなく、毎日お見舞いに通い、会話を重ねられたことが、母の状態を安定させ、認知症の進行を防いだのだと思います。
点滴を受けている最中でも、ここが病院だと認識できなかった母にとって、お見舞いは「自分がどこにいて、なぜここにいるのか」を日々確認できる“命綱”のようなものでした。
気づかれない悪化を防ぐために
入院をきっかけに認知症が悪化するという話は、よく聞きます。
でも今回は、1週間で無事に退院し、今も以前と変わらず過ごせています。
そんな母を見ていると、あの2つの判断――S医師のもとへ戻ること、個室を選ぶこと――が、生死とその後の明暗を分けたのだと、強く感じます。
母の意思のままに動いていたら、そのときは満足できたかもしれません。
しかし、長い目で見れば苦しむことになっていた可能性の方が高かったと、私は思います。
お見舞いは「手間」ではなく「予防策」
お見舞いは片道35分、決して楽ではありませんでした。
でもそのおかげで、母は寂しさを募らせることもなく、認知症の悪化も見られませんでした。
携帯電話を持たせたことで、午前中や夜中にも電話がかかってきて大変でした。
ですが、それも母が不安や寂しさを私に話せた証拠。
その“言葉にぶつける安心感”が、認知症の悪化を抑える力になったと思います。
さらに、家族アルバムや母の伝記、お気に入りの本、新聞などを病室に持って行ったことで、私がいない時間も退屈をまぎらわし、頭を使う時間を確保できました。これもまた、認知症悪化の予防につながったはずです。
非常時こそ、手厚く対応することが、結果的にその後の負担(長期入院や認知症の進行)を防ぐのだと、実感しました。
たった1週間の入院だったけれど、見舞いに通い続けたあの7日間が、母の「今」を守ってくれました。
もしあなたが、認知症の親を抱える立場にあるのなら、
「医療」と「お見舞い」は、どちらも同じくらい大切だということを、ぜひ心に留めてください。

おまけの話:動揺のサイン
実は、緊急入院の翌日。
私はパン屋でサンドイッチを買った時、カード決済で「538」などと、サンドイッチの値段を暗証番号に入力してしまうというミスを犯しました。
暗証番号の入力ミスなんて、この10年間一度もなかったことです。
自分では冷静なつもりでも、内心ではかなり動揺していたのだと気づかされました。
ひと言だけ、言わせてください
※ 入院時の面会を一律で禁止するような対応は、人道に反することだと思っています。
「感染予防」という名目で、患者を人間として扱わないような対応が、認知症の悪化を招くのは当然です。
誰かに会い、話しかけられ、触れられてはじめて、認知症の方は「自分」を保てるのですから。
📝 自分に問いかけてみる時間
-
「親が緊急入院するような状態になったら、私は親にどうしてあげたいか?」という理想を言葉にしてみる。
たとえば、「見舞いに行くことで、相手は何を感じ、何を得るか?」を相手目線で想像する。 -
「見舞いが難しい時、どの手段で“愛を伝える”か?」
(例:手紙、動画・音声、写真など)
📝 簡単なワーク
1 親の体調が急変した場面を想像し、そのとき最初に「行動する3つ」を列挙する
2 1分で、あなた自身が親ならば、見舞いに来てもらって嬉しいこと・いやなことをそれぞれ3つずつ書き出す