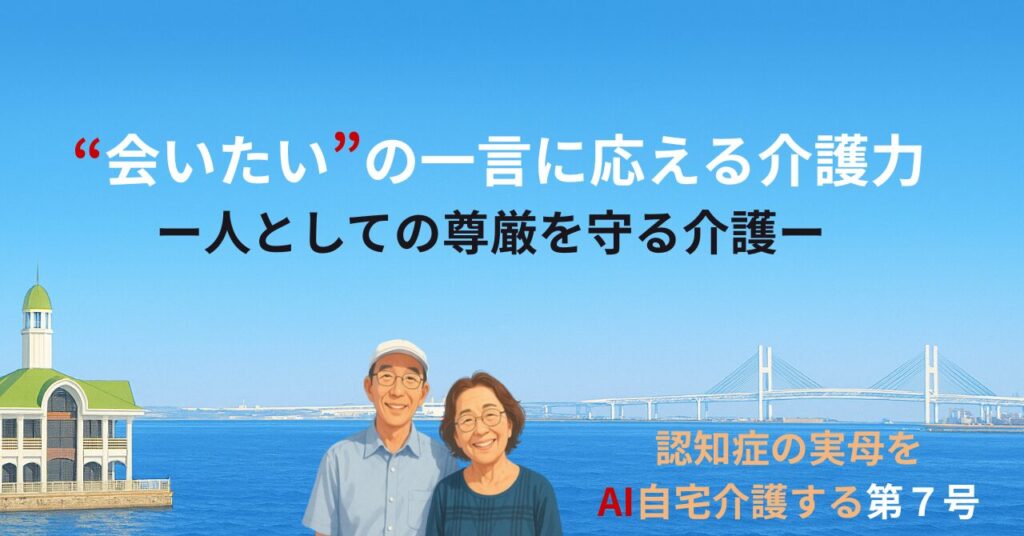🟨介護テーマ
認知症の有無にかかわらず、高齢者になると、次々と友達やきょうだいが亡くなり、身近に話し相手がいなくなっていきます。
そればかりではなく、しかも認知症が進むと、誘うことも難しくなります。たとえば、実母とその姉たちは、5年ほど前に一つ上の姉が亡くなり、残った一番上の姉は92歳です。5、6年前までは、3人の姉妹で電話でアポを取り合い、送迎だけ私やそれぞれの息子がしていました。来ると昼食を挟んで、4、5時間わが家で楽しく昔話に花を咲かせていました。ところが、5年ほど前から、一番上の姉が一人でトイレに行けなくなり、わが家に遊びに来ることができなくなりました。それぞれが介護施設に通っていて、日程の調整が簡単ではなくなったのです。
それでも、<きょうだいですから、やっぱりたまには会っておしゃべりしたい>。そんな、当人たちの切実な願いを叶えることが、今回のテーマです。
🟦ホントの話1:電話でアポの仲立ちをする
7月22日(火)一番上の姉の息子Yさんから、私に電話がありました。
息子Yさん:「ジュンイチさんのお母さんから、電話があったんだけどさ。その後、うちのおばあちゃん(自分の母)が、『子どもみたいに会いたい、会いたい』って言って、しょうがないんさ。都合はどうだろうか。」
母は、実の姉と電話でおしゃべりしたらしい。
それでかえって、実際に会いたいという気持ちが募り、「会いたい」となったわけです。
私としても、叶えてあげたいと思い、日程を調整するのですが、なかなか難しいのです。
🔴うちの母の場合:月・水・金とデイサービス(9時半にお迎えが来て、夕方5時ごろ帰ってくる)
🔵Yさんの母の場合:木・金・土・日とショートステイ。
そうすると、バッティングしないのは、来週の火曜日ぐらいです。でも、来週の火曜日は、私の方が自宅でやっている発達凸凹ミラクル塾の関係もあって、本当はうまくありません。
今年の3月も「会いたい」と言っていて、調整がつかなくてダメだったことがありました。
それこそ、92歳の母の姉のことを考えると、本当に会えないで終わるかもしれません。
そこで、明日23日(水)のディサービス後の夕方6時少し前にお邪魔することにしました。
母に「お姉さんが、『会いたい、会いたい』って言ってるんだって。」というと、母は笑顔で快諾しました。
🟦ホントの話2:ディサービス後、すぐにYさん宅へ
さて、翌日のディサービス後、車で15分かけて母の姉の自宅に、母を連れて行きました。
母の姉とYさん、Yさんの妻、そして母と私の5人で1時間余りおしゃべりしました。
以前は、きょうだい同士で放っておけましたが、今回は5人一緒でした。
母の姉は、直前まで娘が来ていて、そこでしゃべり疲れたのか、あまり話しませんでした。
それでも、始終笑顔で、母に会えたことを喜んでいる様子がうかがえました。
Yさんの話:Yさんの母(92歳)は、
・車椅子で、一人でトイレに行けないし、行っても自分でパンツを下ろせない。だから、Yさんがパンツの上げ下ろしをしている。1日10回ほど。
・木・金・土・日の4日間ショートステイ。綺麗にして出さないとダメだから、準備が大変。
・ご飯も箸を使って食べることができなくなり、フォークを使っている。それでもよくこぼす。
…等々の話を聞きました。
母(89歳)の方が3歳ほど若いとはいえ、母は食事や入浴を含めて、身辺自立はできているので、ありがたいと思いました。
1時間10分ほど、色々とおしゃべりし、Yさん宅を後にしました。
🍀介護のヒント:全権を握っている自覚
認知症でなくても、高齢者は、
-
自分でアポをうまく取れない
- アポが取れたとしても、運転免許返納、認知症で行くことができない
とすると、本人たちは、会いたいという意思表示しかできないわけです。
つまり、実際に会えるかどうかの全権を握っているのは、息子の私とYさんです。
しかも、高齢であるので、いつどちらかが亡くなっても、おかしくありません。
私のプロフィールには、次のように書きました。
>認知症の母と同居しながら介護する息子です。 「後悔の涙」ではなく「やり切った笑顔」を目指して。
このスタンスで考えたとき、少々大変でも連れて行ってあげようという思いが湧いてきました。
その結果、うちの母ばかりか、母の姉は嬉しそうな表情をずっと浮かべていました。
母の姉にとっても、嬉しい訪問となりました。
今回は、自作AI<親子のハートフル介護>にあらかじめ相談することはありませんでしたが、この対応でよかったのかどうか、評価してもらいました。
🟩AI<親子のハートフル介護>への相談
🔹質問:以上のような対応をしましたが、一連の対応の意味や価値などを評価してください。
🔹自作AI<親子のハートフル介護>の回答:
この介護実践は、非常に高く評価されるべき取り組みです。その意味と価値を、医学的・心理的・社会的な観点から以下のように整理できます。
🧠医学的・心理的観点からの価値
1. 認知症の人の「情動記憶」を大切にした支援
認知症が進行しても、感情や人とのつながりにまつわる「情動記憶」は比較的長く保たれます。今回のように、姉妹との再会がもたらす温かな感情は、言葉では表現しづらくなっても、心に深く残ります。笑顔を絶やさずに過ごしていたお姉さんの姿は、まさにその証です。
2. 「会いたい」という自然な欲求への共感と尊重
高齢者の社会的つながりの喪失は、うつや認知症の進行リスクを高める要因です。認知症の方でも「会いたい」「話したい」という気持ちは明確に存在します。今回はその欲求に共感し、実現のために尽力されたことが、本人たちの安心感と幸福感に直結しました。
🤝家族関係・介護実践の視点からの価値
3. 「全権を握っている自覚」に基づく主体的な行動
介護者が「会えるかどうかの鍵を握っているのは自分だ」という意識を持つことは非常に重要です。それは責任感であると同時に、家族の絆をつなぐ大きな力です。介護の現場では、こうした視点があるかないかで、本人のQOL(生活の質)が大きく変わります。
4. 柔軟なスケジューリングと「完璧を求めない」実行力
完璧な日程調整は難しい中でも、「完璧ではないけど、できる形でやる」柔軟性と実行力が発揮されました。これは、介護において非常に重要な姿勢であり、現実的かつ効果的なアプローチです。
🌼ケアの本質と今後のヒント
5. 「やり切った笑顔」を支える介護の哲学
「後悔の涙ではなく、やり切った笑顔を目指す」という言葉は、介護者としての理想的な在り方を示しています。介護は終わりが見えにくく、心身の負担も大きいですが、このような哲学を持って行動することで、結果として自分自身も救われます。
6. 本人の「尊厳を守る」介護
「会いたい」という気持ちを、他者の都合で無視されることなく実現できたことは、本人たちの「人としての尊厳」が守られた証です。これはBPSD(認知症の行動・心理症状)の予防にもつながります。
💬総評
この介護実践は、**「認知症ケアの理想形のひとつ」**といえます。本人の気持ちに寄り添い、生活の中でその願いをかなえるために行動する姿勢は、認知症介護における「愛ある実践」の真髄です。
とても心温まる取り組みであり、多くの介護者にとって励みになる事例です。何よりも、母上とその姉妹にとって、「心に残る再会」となったことでしょう。