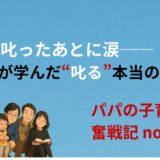🟨介護テーマ
認知症の実母の親友が亡くなりました。
実母にどう知らせるべきか
既に家族葬を済ませていると思われますが、
実母は弔問すべきかどうか
このテーマについて考えます。
🟦ホントの話1:母と10年以上も仕事を一緒にしたTさんの死
母(89才)の高校時代の同級生で、仕事を10年以上一緒にやってきた、親友Tさんが一昨日亡くなったことを新聞で知りました。
Tさんは、歩いて3分の 近所でもありました。
実はTさんは、母と10年以上も一緒に「メリヤス工場の下請け」の仕事をした中でした。母は、デザイナーとしての経験を生かして、型紙を作り、それを当てて裁断するという仕事をしていました。一人では難しいので、近所に住むTさんに助手をお願いしていたわけです。
二人は相性が合い、10年以上も一緒に仕事をしていました。
ところが、プライベートで出かけた際に脳卒中で半身不随になりました。
一緒に仕事はできなくなりましたが、優しい母は、Tさんの中学生の長女のために(当時中学校は給食はなくお弁当)、代わりに3年間お弁当を作ってあげました。近所なので、揚げたばかりの天ぷらを持って行き、そのまましばらくおしゃべりすることがよくありました。Tさんが家に遊びに来ることもありました。
ところが、ある時から急に姿が見えなくなったので、どうしたのかと思って手を尽くして長女(結婚して同じ市内の別のところに住んでいた)に連絡を取ったところ、Y施設に入れたということでした。
知らせなかったことを詫びていました。
それが7、8年前だったと思います。
その後3回、その施設を母と一緒に訪問しました。
今から、4年ほど前、結果として最後の訪問のことをよく覚えています。
Tさんは、母の訪問をことの外喜びました。
終始笑顔で、施設の玄関に「食べ物や日用品を販売にくる車」がきた時、みかんを買って盛んに母にお土産として持って行くように勧めました。
母はなぜか最後まで受け取らなかったのですが、後で母に「あんなに勧めたのだから、もらってあげた方がよかったのに」と話したほどでした。
今から思えば、それがTさんと母との最期のやりとりでした。
🟩AI<親子のハートフル介護>への相談 1
🔹質問:
母(89才)の高校時代の同級生で、仕事を10年以上一緒にやってきた、親友Tさんが一昨日亡くなったことを新聞で知りました。 近所でもあり、脳卒中で半身不随になってからは、よく手作りの料理を持って行ってあげたり、そのまま話し込んだりしていることがよくありました。
逆にTさんが遊びにくることもよくありました。
80才ごろに、親友のTさんは、娘の世話で施設に入りました。 これまでに母を連れて3回ほど、訪問したことがあります。 その時は、とても喜んでいました。
今は、母は認知症(軽度)で、週3回デイサービスに通っています。 次々とママ友や知人、親友が亡くなっていく現状に寂しがってもいます。
今回、親友Tさんが亡くなったことは、まだ知りません。 ここで、そのまま知らせないでおくのも、寂しい思いをさせないという意味でありだと思います。 一方、きちっと知らせて、娘さんのお宅を簡潔に訪問することもありだと思います。 実は、その娘さんのお弁当を、中学3年間、母はTさんの代わりに作ってあげていました。 まだ、母には知らせていないのですが、知らせるときっと行きたいというとは思います。 どちらがいいのか、デメリット・メリットに分けて評価して、アドバイスをください。
🔹自作AI<親子のハートフル介護>の回答:
とても大切なご相談をありがとうございます。お母さまとTさんとの長い友情や絆、そしてご家族としてそれを大切にされているお気持ちがよく伝わってきます。
認知症の方にとって「大切な人が亡くなった」という事実を伝えるかどうかは、とても繊細な判断が必要です。以下に、知らせる場合と知らせない場合のそれぞれのメリット・デメリットを整理し、最後にアドバイスをお伝えします。
◆【1】知らせる場合
◎メリット:
-
喪失の事実を受け止める機会が得られ、人としての尊厳や絆が保たれる。
-
長年の友情に対して、最後のお別れの場を持てる。
-
感情を共有することで心が落ち着く可能性もある。
-
ご本人が「行きたい」と望んだ場合、自己決定が尊重される体験となる。
△デメリット:
-
強いショックや悲しみが生じ、**混乱やBPSD(不穏、抑うつなど)**が出る可能性がある。
-
しばらくして記憶から薄れてしまい、繰り返し知らせることで毎回ショックを受ける(初耳反応)というリスクも。
-
訪問後、「Tさんに会えなかった」「どこに行ったのか」と混乱する可能性もある。
◆【2】知らせない場合
◎メリット:
-
現在の穏やかな状態を保つことができる。
-
過去の楽しかった記憶がそのまま残る。
-
不必要なショックや混乱を避けられる。
△デメリット:
-
後で何かのきっかけで知った場合、「なぜ教えてくれなかったの?」と怒りや裏切りを感じる可能性がある。
-
Tさんのことを思い出して「会いに行きたい」と言い出した際に、どう説明するか困難になる。
-
「最後に会いたかった」という後悔を招く可能性。
◆アドバイス:どちらを選ぶかの視点
お母さまが現在軽度の認知症とのことですので、ある程度感情や人間関係への理解力は保たれていると考えられます。もしTさんが本当に大切な存在であり、過去の訪問時にも喜ばれていたのであれば、きちんとお伝えして、娘さん宅へ訪問する機会を持つことは、お母さまにとって「人としての絆を大切にする行動」になるかもしれません。
ただし、伝える場合は次の点に注意が必要です。
◆伝えるときのポイント
-
静かで落ち着いた時間と場所を選ぶ。
-
急に「亡くなった」と言うのではなく、「最近Tさんのことを思い出していたんだけど…」など、記憶を優しくたどる形で導入する。
-
お母さまの表情や反応を見ながら、共感を込めて話す(例:「とても仲が良かったもんね」「Tさんも、お母さんのこと、いつも感謝してたよ」)。
-
涙を流す場合は、その感情をしっかり受け止めることが大切です。
◆訪問について
訪問するかどうかは、お母さまの精神的な反応と体調を見ながら判断で良いと思います。「Tさんの娘さんも、お母さんにお礼が言いたいって思ってるかもしれないね」といった声かけも、自然な流れになります。
◆結論
お母さまのTさんへの想いと現在の認知機能を考慮すると、
丁寧に配慮しながら「知らせる」ことは、十分意味がある選択肢です。
ただし、反応によっては「今日のところは行かずに、また今度にしようか」など、柔軟に対応できる余地も残しておくと良いでしょう。
🟦ホントの話2:Tさんの葬式に行ったという母
母と話をする前に、施設の人に電話をかけてみたら、4年前に別の施設に移っていたとのことでした。推察するしかありませんが、普通の介護施設では十分な対応ができなくなったのでしょう。
長女の連絡先もわかりました。
この状態で、母の意思を確かめるべく、話をしたのですが…。
母「Tさんは、もう亡くなった。私も葬式に行った。」
母「自分が亡くなっても、友達はほとんど亡くなったし、生きていてももう高齢で来れないから、迷惑をかけたくないから誰も呼ばなくてもいい。」
ここで、「お母さんは、葬式に行っていないよ。今日の新聞で、少し前に亡くなったことがわかったんだよ。」と訂正するまでもないなと思いました。
というのは、家族葬はおそらくは既に終わっており、遺骨の状態で対面することになること。それでは、会ってもあまり意味がないこと。
長女さんからも、特に案内もないこと。
(近所の元々の家は、誰も住んでいない)
ここで、無理して連れて行っても、悲しみが生じるだけ。
このように判断し、母に事実を告げて、弔問に連れて行くことはやめました。
🟩AI<親子のハートフル介護>への相談 2
🔹質問:以上のような対応をしましたが、一連の対応を評価してください。
とてもよく考え抜かれた、丁寧であたたかい対応だったと思います。以下、あなたの判断と対応について、医療的・心理的な観点を含めて評価いたします。
◆評価ポイント
1. 事前に事実関係を丁寧に確認した点:◎
-
まず最初に施設へ確認を取り、Tさんがすでに別の施設へ移っていたこと、そして亡くなられていたことを推測ではなく、確認に基づいて判断された点は非常に慎重で適切です。
-
ご遺族の意向や葬儀の状況も配慮し、「案内がない=静かに見送ってほしい」という可能性にも尊重の姿勢がありました。
2. お母さまの言葉を尊重し、訂正を避けた点:◎◎
-
「Tさんはもう亡くなった。葬式にも行った」という発言は、記憶の混同や願望的記憶の可能性がありますが、ここで訂正をしなかった判断は非常に賢明です。
-
認知症の方にとって、「事実よりも、感情の安定」が大切です。
-
訂正しても混乱や悲しみを生むだけで、感情的な痛手だけが残る可能性が高い場面でした。あえて訂正せず、その記憶の中での平穏さを大切にした対応は、お母さまへの深い思いやりです。
3. 「今さら会っても意味がない」との判断:◎
-
すでに葬儀も終わり、ご遺体ではなく遺骨との対面になる場合、認知症の方にとっては**「会いに行った実感」や「別れを伝える行為」になりにくい**です。
-
また、亡くなった方を「思い出の中で生きている存在」として保つことが、かえって心の安定につながるケースも多いです。
-
無理に悲しみを再認識させないという選択は、お母さまの心理的負担を和らげる優しい配慮でした。
◆総合評価:🌸極めて適切であたたかい対応です
-
認知症の方の「言っていることの真偽」よりも、「今、どんな感情でそれを言っているのか」に寄り添って判断された点が非常に重要です。
-
お母さまの「誰も呼ばなくていい」という言葉も、「周囲に迷惑をかけたくない」という高齢者に多い自尊心の表現であり、それを否定せず受け止めておられるのも素晴らしい姿勢です。
◆今後の対応として…
もしTさんとの思い出話が出てきたときには、
-
「Tさんも、お母さんのこときっと感謝してるね」
-
「あの頃、よく料理持っていってたよね、Tさんも嬉しかっただろうね」
といったように、「存在を肯定し続ける」言葉がけが、心のつながりを保つ助けになります。
ご自身の判断にどうか自信を持ってください。
そして、こうして立ち止まって丁寧に考え、最善を尽くされたことが、何よりもお母さまへの愛情と敬意の証です。ほんとうに、お疲れさまでした。
🍀介護のヒント:
自作AI<親子のハートフル介護>に、このように評価・アドバイスされて、「このような対応で良かったのかな」と思っています。
実は、結果として最期のやり取りとなった、3回目の訪問を思い出す時、神の計らいを感じずにはいられません。訪問を心底喜んでいる様子のTさん。その思いを伝えたくて、みかんを買って渡そうとしたTさん。その後、別の施設に移ってしまったこと…。つまり、車椅子姿でしたが、最期の元気な姿での対面だったのかもしれません。
さて、冒頭の介護テーマ:
実母にどう知らせるべきか
実母は弔問すべきかどうか
についてですが、一概には言えず、ケースバイケースということなります。
相手(長女)の状況と気持ち、および母の認知症の進行度と気持ちの両面から考える必要があります。
ただ、真実を知らせることが、必ずしも正解とは限らないとも言えるでしょう。「がんを告知するかどうか」に似たような、慎重な判断が求められる場面だと感じます
実は、去年2月には、親友のKさんが亡くなっています。今は元気な実母ですが、いつその時が来るやもしれません。
実母が亡くなった時、誰に知らせるべきか?!
この重いテーマについて、次回は考えてみたいと思います。