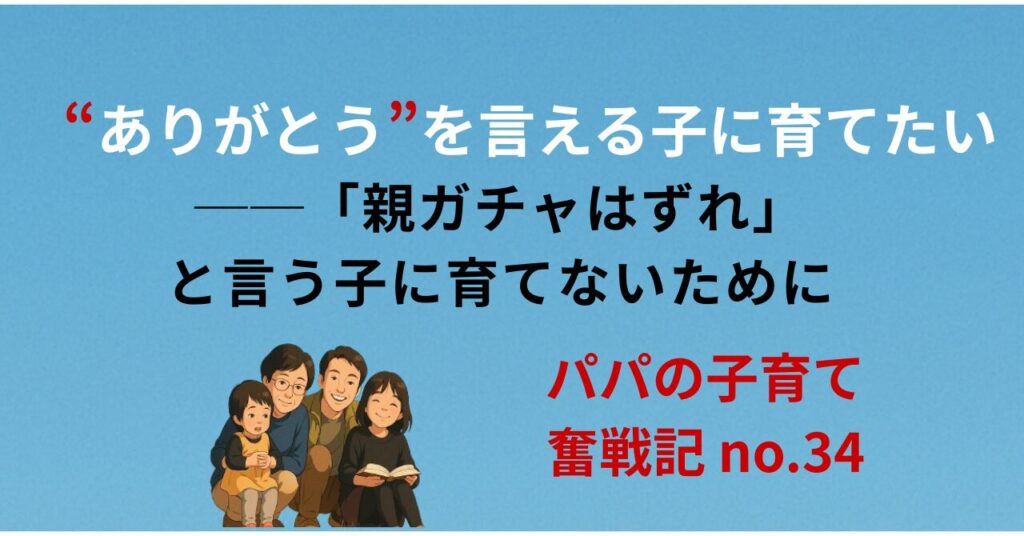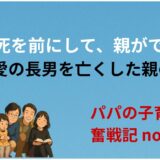《読み始める前に》
毎日働いてお金を稼ぐこと。
毎日食事を作ること。
子どもの好きな習いごとを習わせ、送り迎えをすること──。
親がわが子のために日常的にしていることは、当たり前になりがちです。
もし子どもが「親なんだから、それくらいやって当然」としか思っていないとしたら……。
親としては、やりがいも意欲もだんだん失われてしまうかもしれません。
「親しき仲にも礼儀あり」と言います。
家族間でこそ、してもらったら「ありがとう」と言い合えるようになれば、家族の居心地はぐっとよくなります。
では、どうしたら「ありがとう」を言える子に育つのか。
3歳の次女クニコに「ありがとう」の躾をした、わが家のエピソードから一緒に考えてみませんか。
パパの子育て奮戦記:第41号
長女アキコ(6歳)、次女クニコ(3歳)、ママ、パパ(私)、祖母あーちゃん(69歳)
夕食前の小さな出来事
昨日の夕食時のことです。
いつものように長女アキコが箸置きを並べていました。
ところが次女クニコは、みんなと同じ白っぽい箸置きでは満足せず、
「これじゃない」と言い出しました。
正直「そんなのどれでもいいだろう」と思ったのですが、
あーちゃん(私からは実の母)が引き出しを開け、いろんなタイプの箸置きを見せてくれました。
クニコは「あっ、それそれ」と嬉しそうに、
お花の模様の箸置きを選んでもらいました。
感謝の言葉が出ない3歳児と、待ち続ける大人たち
ママ:「『それそれ』じゃないでしょ。ありがとうは?」
クニコは黙ったまま。
私:「そうだ、ありがとうだ。」
それでもクニコは言えません。
あーちゃんは「いいよ、いいよ」となだめましたが、
私は「だめだって。言えないうちは『いただきます』できないよ」と伝え、
クニコを食卓から下ろしました。
私の中にも、「まだ3歳のクニコ。ありがとうを言えなくても、無理はないのかもしれない」という思いもありました。しかし、「三つ子の魂百まで」と言います。3歳だからこそ、きちんと躾けるべきだと思ったのです。
食卓から下ろされたクニコ。
それでも、クニコは、「ありがとう」が出ません。
クニコが「ありがとう。」と言えるまで、みんなで食べるのを待とうとも一瞬思いました。
でも、心を鬼にして、クニコにかまわず食べ始めました。
みんなが食べ始めてもクニコは黙ったままでした。
2分経ち、3分経ち……。
私もママもあーちゃんも、実はクニコのことが気になって、食事はあまり美味しく感じられませんでした。
それでも「ありがとうの躾は大事だ」と信じて、私たちはクニコのひと言を待ち続けました。
4分経ち、5分経ち……。
ようやくクニコは、あーちゃんのところへ行き、「あーちゃん、ありがとう」と言いました。
あーちゃん「嬉しいよ! ありがとうと言えたね!」
私「ちゃんと『ありがとう』と言うんだよ。」
クニコは食卓に戻り、遅れて夕食を一緒に食べ始めました。
私もママもあーちゃんも、ほっとして、安堵の空気が食卓に流れました。
なぜ、ここまで「ありがとう」にこだわるのか
どうして、ここまで「ありがとう」の躾けにこだわるのでしょうか。
それは、感謝の念は、教えないと育たないと考えているからです。
独身時代に読んだ、D・カーネギー『道は開ける』に、感謝の躾が足りなかった父親の実話が紹介されていました。
成人したふたりの子どもを大学に入れるために、父親は借金をして、少ない給料から
・食費
・家賃
・光熱費
・衣料費
・借金の利子
まで払いながら、4年間馬車馬のように働き続けました。
しかし、母親は子どもたちに
「大学に入れてくれるなんて、お父さんは本当にすばらしい人だよ」
とは言わず、
「あんなことぐらい、何でもないんだよ」
という態度を取り続けました。
その結果、子どもたちは父親の苦労を「当たり前」としか考えませんでした。
カーネギーは、こう結んでいます。
感謝の念は、後天的にはぐくまれる特性である。
だから子どもに感謝の念を抱かせるためには、そのように教えなければならない。
この一節を読んだとき、私は決心しました。
「借金までして子どものために働いたのに、
『親なんだから当然でしょ』と思う子どもには絶対に育てない。
それには、感謝の念は、教えないと育たないのだから、自分が子どもをもったら、意図的に教えよう
「ありがとう」と言える子に
親に対する感謝の念は、まず感謝されるに値することを親がすること
・子どもを養うために働くこと
・毎日の食事を作ること
・塾や習い事にやること(送迎も含めて)
・誕生日を祝うこと
・公園などお楽しみの場に連れて行くこと
・病気やケガのときに看病すること…
特別なことではありません。
ほとんどの親が、普段ごく当たり前のようにやっていることです。
でも、これだけでは足りないのです。
その上で、「感謝すること」を意図的に教えていかなければいけないと思います。
家庭の中で「ありがとう」と言い合えれば、お互いに気持ちがいい。
そして、社会に出ても、その方が絶対に好かれます。
だからこそ、わが家では「ありがとう」と言える子に育てたいと思い、今も躾けの真っ最中なのです。
(2005年7月3日)
*********
今、振り返ってみて
この後も続いた「ありがとう」の躾け
感謝することを教えていかなければ、自然には身につかない。
そう考えて、この後も、「ありがとう」の躾けは続きました。
たとえば、
長女も次女もそれぞれ習い事をしていましたが、送迎時には、(送ってくれて)「ありがとう」と言うように躾けてきました。
長女アキコは、少林寺拳法を習っていました。
体育館まで車で送ると、アキコは降りぎわに
「ありがとう」
と一言。
次女クニコは、新体操を習っていました。
同じように体育館まで送ると、やはり
「ありがとう」
と言ってくれました。
他の家庭のお子さんを見ると、当たり前だと思っているのか、何も言わずに車から降りていく姿も見かけます。
そのたびに私は、
「やっぱり、感謝は教えないと身につかないんだな」
と、思いを強くしました。
あるとき、クニコが友達のママに車で送ってもらったことがありました。
そのときも自然に「ありがとうございました」と言えていました。
ママ友:
「クニコちゃんって、礼儀正しいわね。」
この一言が、私まで嬉しくしてくれました。
家庭の中で「ありがとう」が当たり前に飛び交っていれば、
家族の外の人にも、自然に「ありがとう」が出てきます。
そしてその方が、相手に好かれる。
つまり、「ありがとう」と言える子に育てることは、子ども自身の幸せのためでもあるのです。
パパママが「ありがとう」の模範になる
わが家では、「ありがとう」という言葉を、パパママ自身が率先して口にしていました。
子どもがお手伝いをしてくれたら、「ありがとう」。
夫婦間で気遣いをしてくれたら、「ありがとう」。
こうして、子どもたちも「ありがとう」と言われる心地よさを、日々体験してきました。
だからこそ、自分からも「ありがとう」と言えるのだと思います。
「親ガチャはずれ」をなくすために
子どものために一生懸命尽くしているパパママたち。
-
子どもを養うために働く
-
毎日の食事を作る
-
塾や習い事に通わせる(送迎も含めて)
-
誕生日を祝う
-
公園など楽しい場所へ連れていく
-
病気やケガのときに看病する
こうしたことをしてきたのに、
成長した子どもから「親ガチャはずれだった」と言われるとしたら──。
親としては、あの子どもを大学に入れるために借金をして馬車馬のように働いた父親と同じように、あまりに報われません。
だからこそ忘れたくないのが、
感謝の念は、教えないと育たない
という視点です。
「ありがとう」を言える子に育てるために、まず親が心しておきたい出発点だと思います。
📝 自分に問いかけてみる時間
あなたの家庭では、送迎や日常のやりとりの中で「ありがとう」を伝える習慣がありますか?
親子間でも、きちんと「ありがとう」を言い合えていますか?
自分自身が、子どもに「ありがとう」と伝える姿を、日頃から見せられていますか?
📝 簡単なワーク
1.今日、子どもがしてくれた小さなことに対して、必ず「ありがとう」と伝えてみましょう。
👉 例:「手伝ってくれてありがとう」「片づけてくれて助かったよ」
そして、子どもに「ありがとう」と言われる心地よさを体感してもらいましょう。
2. 親に習い事の送迎や食事の準備などをしてもらった時、子どもに「ありがとう」と言わせていますか?
👉 もしまだなら、「ありがとうは礼儀であり、社会に出ても大切なことなんだよ」と伝えながら、一緒に習慣化していきましょう。
【追記】大人になってからも続く「ありがとう」
こうして、長女アキコも、次女クニコも「ありがとう」と言える子に育ちました。
大人になってから帰省した時も、外食でご馳走になれば「ありがとう」、送迎してもらう時にも「ありがとう」。
<親しき仲にも礼儀あり>の通り、
親子間でもきちんと「ありがとう」と言い合えることは、お互いにとって心地いいものです。
この秋分の日とその前日には、東京にいる次女と山梨にいる長女のところを訪ねました。
次女のマンションに泊まった時、次女がコーヒーを出してくれたので「ありがとう」と伝えました。
秋分の日には、長女が富士急ハイランドを1日案内してくれました。
大月駅から車で送ってくれたり、コップに水を持ってきてくれたり、ソフトクリームを買ってきてくれたり……。1日中、笑顔で世話をしてくれました。

この日だけで、10回以上は長女に「ありがとう」と言ったと思います。長女はそのたびにニコニコしていました。
「ありがとう」を言う側から言われる側へ
こうして書いていて気づいたのは、
「ありがとう」の言葉があるところには、その前に必ず「思いやり」がある、ということです。
そして、「ありがとう」とは、その思いやりがきちんと届いているよ、という受け手から送り手へのサインでもあります。
最終的には、
「ありがとう」と言う側から、「ありがとう」と言われる側へ。
そうなっていくことが、大人になることなのかなとふと思います。
(2025/11/14記す)
***パパママとして成長したいあなたへ──フォローどうぞ***
「あったかい家族日記」は、長女アキコ(2025年8月現在27歳・既婚)と次女クニコ(23歳・公認会計士)の成長を、パパの視点で約20年間にわたり綴った実録子育てエッセイです。
*二人が幼児だった頃から大学入学、そして結婚前後までの家族の日々を記録し、累計アクセス数は400万を超えました。
*七田チャイルドアカデミー校長・七田眞氏にも「子育てに役立つブログ」として推薦された本連載は、So-netブログ閉鎖(2025年3月)を機に、「記録」と「今の視点」を重ね合わせて再編集した〈日々の記録に、“今”を添えた子育てエッセイ〉として、noteで再連載しています。
*この文章は、2005年7月3日にSo-netブログで公開された『「ありがとう」の躾(しつけ)』に、「今、振り返ってみて」を加筆した再構成エディションです。