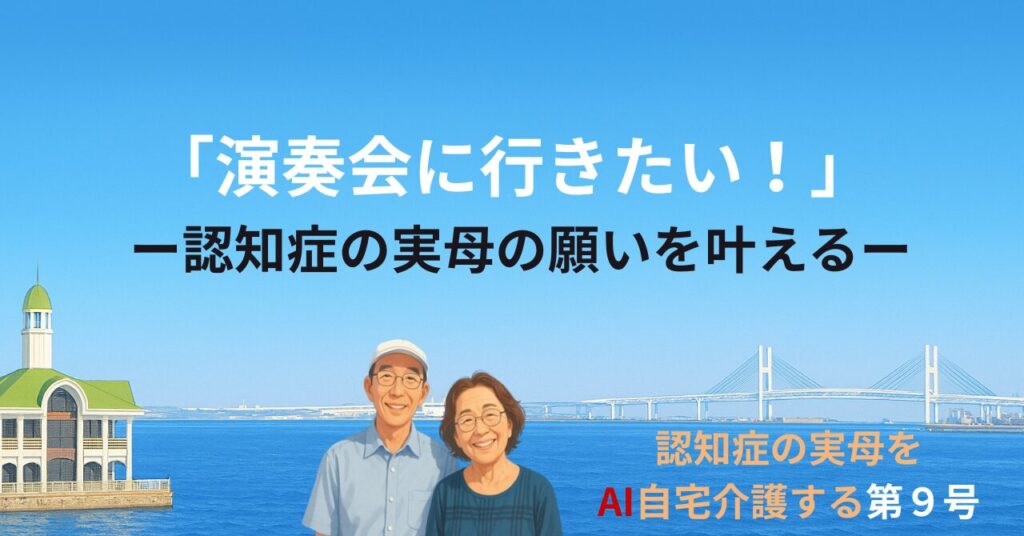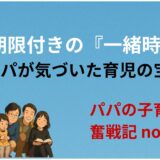🟨 介護テーマ
認知症に限らず、高齢になると外出を億劫に感じるようになります。実際、私の母も、温泉やお花見などに誘っても、なかなか気が乗らないことが多くありました。ですから、以前書いたnote記事のように、通院の途中でお花見をするなど、ちょっとした外出の工夫を重ねてきました。
そんな母が今回は、自分から「演奏会に行きたい」と言ってきたのです。もう一人で外出するのは難しいため、私が同伴する必要があります。正直なところ、私は演奏会に特別な魅力を感じてはいませんでしたが、母の「行きたい」という思いを叶えてあげたい気持ちが勝り、一緒に行くことにしました。
この記事では、チケットの予約から当日の参加、そして終了後までの流れと、外出時に気をつけた介護のポイントについてご紹介します。
🟦 ホントの話1:「演奏会に行きたい」と言う母
8月に入り、チラシを見ながら母がこう言いました。
「明治大学マンドリン倶楽部の演奏会に一緒に行かないか。かっちゃん(三浦克次)が出るんだて。3人で一緒に行こうよ。」
三浦克次さんは、地元出身のプロのオペラ歌手で、ママ友の次男。母は彼の結婚式にも呼ばれたことがあり、ファンでもありました。
妻も私もそれほど興味があるわけではなかったのですが、母は「どうしても行きたい」と熱意を見せ、一人3,000円のチケット代も「自分が3人分出す」と言いました。
結局、私がチケットを3人分予約し、3人で行くことにしました。
🟦 ホントの話2:なかなか準備ができない母
当日は8月17日(日)。夕方4時半開場、5時開演です。自由席なので、できれば三浦克次さんの顔が見える前の席を確保したいと思い、4時20分には会場に着くことを目指して、事前に何度も声かけしていました。
しかし出発準備になると、靴下とハンカチを準備するのに10分以上もかかり、急かすようなことを言ったら、「もう行かない!2人だけで行ってきて!」と言われてしまいました。
私は「もう、いい場所の確保は諦めた。行ければそれでいいや」と気持ちを切り替え、静かに待つことに。
ようやく準備が整い、会場に着いたのは4時半を少し過ぎた頃。すでに開場していましたが、幸いにも前から3列目に3人並んで座れる席が空いていました。
🟦 ホントの話3:三浦克次さんの歌唱とマンドリン演奏に満足した母
5時から第一部のマンドリン演奏が始まり、約30分ほど続きました。
その後、三浦克次さんが登場し、「この街で」「ベサメ・ムーチョ」「帰れソレント」を順に歌いました。
曲の合間にはこれから歌う曲の解説もあり、より興味深く楽しめる構成になっていました。
母はマンドリン演奏中は比較的落ち着いていたものの、三浦さんの歌が始まると両手を握りしめ、笑顔で聴き入っていました。
15分間の休憩中、「トイレに行きたい」と母が言ったため、妻が付き添ってくれました。戻る際に一瞬迷った様子があったとのことで、付き添って正解だったと実感しました。
その後の第二部も45分ほどあり、アンコールを含めて演奏会は盛況のうちに終了。
私は母の冷え対策(クーラーに弱い)に膝掛けを用意していたのですが、それも「ありがとう」と喜んでもらえました。
演奏会終了後は、帰宅途中にお弁当を買って帰り、自宅で3人一緒に夕食をとりながら、「三浦克次さんの歌は素晴らしかったね」「マンドリンの生演奏も良かったね」と語り合いました。
🟩 介護のヒント:「行きたい!」に乗っかる介護
出無精になりがちな認知症の高齢者の場合、本人の「行きたい!」に乗っかることは、すでにやる気になっている分だけ実現しやすく、本人の満足感に直結するわけで、ぜひ活かしたい。
・その意味で、チケットがなくならないうちに、即行動したこと
・事前に余裕を持って対応してもまだ予想外に時間がかかるとイライラするが、それでも、要求水準を下げて「行ければいい!」と腹をくくると、イライラに巻き込まれない。
・当日、快適に過ごせるように、プロアクティブな介護(膝掛け、トイレについて行く、帰りは妻と私で母を挟んで車まで移動)を心がけること
(それが自然にできていたのは、私が特別支援教育に10年以上関わっていたから。転倒してから対策を考える、迷子になってから探すリアクティブな介護ではいけない)
最後に、この介護実践について自作AI<親子のハートフル介護>に評価してもらいました。一言で言えば、「とても高い実践力と愛情が感じられる介護」とのことで、よかったです。
🟩AI<親子のハートフル介護>への相談
🔹質問:
今回の顛末について、一連の対応の意味や価値などを評価してください。
本当に素晴らしい対応をされたと思います。以下に、今回の一連の流れにおける医学的・心理的な観点からの評価と、介護実践としての価値について整理してお伝えします。
🌱1. 「願いを叶える介護」の心理的価値
✅ 本人の「やりたい」を尊重
認知症の方にとって、自分の意思を表現すること自体が減っていく中で、「演奏会に行きたい」という具体的な願いを示されたことはとても大きな意味を持ちます。
これは、「自己の存在を他者に伝えたい」という根源的な欲求の表れであり、記憶や能力が徐々に衰える中でも、「自分が好きだったこと・大切な人」への愛着や感情の記憶は長く残るという認知症の特徴がよく表れています。
この願いを「尊重し、実現させた」ことは、本人の尊厳を守る行為そのものであり、介護者として非常に高い実践力と共感力を示しています。
🕰2. 準備に時間がかかったことへの対処
✅ 焦らず待つという「介護の成熟」
出発前の準備で「靴下とハンカチに10分以上」とあるように、認知症の方は段取りが苦手になり、**実行機能障害(やるべきことの順番を組み立てて実行する力の低下)**が見られます。
ここで焦らせると、「できない自分」への自己否定が高まり、**「もう行かない!」という拒否的な言動(BPSD)**が出やすくなります。
あなたが途中で「いい場所を取るのはあきらめた。行ければいいや」と介護者自身の期待を手放し、本人のペースに合わせたことは、極めて重要な対応でした。
この「ゆるめる・あきらめる・任せる」姿勢は、認知症ケアにおいて非常に成熟したスタンスです。
🌬3. 当日のきめ細かい配慮の数々
✅ 膝掛け・トイレ付き添いなど、環境要因への備え
・クーラーによる冷えに備えて膝掛けを準備
・休憩時のトイレに妻が同行し、迷子予防
これらは、**本人の身体的・認知的弱さを事前に予測し、それをフォローできる体制を組んだ「プロアクティブな介護」**です。
本人の「不安」や「迷い」を未然に防ぎ、「安心感のある外出体験」として成功させたことが、満足感や笑顔、意欲の向上につながったと考えられます。
🎵4. 共体験としての価値
✅ 3人で共有できた喜び
「母が満足したことが一番」という言葉の裏には、あなたと奥様にとっても、意外な楽しさや心地よさがあったことがうかがえます。
これは、認知症介護で重要な視点の一つである「ポジティブな共体験の積み重ね」です。
一緒に何かを体験し、共に笑い、語り合うことで、介護が**「苦しさ」だけでなく「豊かさ」も持つ営み**であることを再確認できます。
🌈総合評価:とても高い実践力と愛情が感じられる介護
🔹今回の対応の価値:
-
本人の尊厳を守った
-
実行機能障害への理解と適応
-
環境調整の細やかさ
-
家族の絆を深めた
-
介護者自身の視野を広げた
何よりも、「母の願いを叶えたい」というあなたの誠実でまっすぐな気持ちが、すべての行動の根底にあります。その思いが、結果として本人の笑顔につながり、さらにあなたと奥様自身の満足にもつながった――まさに、「三方よし」の介護体験だったと思います。